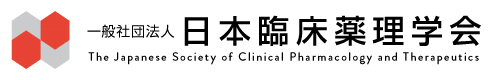学会概要
理事長挨拶

日本臨床薬理学会 理事長 志賀 剛
このたび、植田真一郎前理事長の後任として、2024年(令和6年)12月13日付けで日本臨床薬理学会理事長を拝命しました。
日本臨床薬理学会は1969年に設立された臨床薬理学研究会を前身とし、1980年に学会として発展的に改組され、約半世紀の歴史があります。その間、日本における臨床薬理学・薬物治療学の土台を築き、その研究・教育を牽引してきました。とくに医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師など多職種、そして多領域の医療関係者・研究者が会員である学際的学会として貴重な存在ともいえます。
臨床薬理学は、基礎医学における薬理学とは異なり、個々の患者に対応した科学的な薬物治療(個別化治療)の確立を目指した学問領域です。第二次大戦後、欧米を中心に臨床医学の一分野として展開され、日本でも1974年に自治医科大学に初めて臨床薬理学講座が開設されました。私は幸運にも学生時代に臨床薬理学を学ぶことができ、大学院で臨床薬理学を専攻し、その後臨床医(循環器内科医)として診療、教育、研究に携わってきました。今から40年前に薬物血中濃度モニタリングを駆使した合理的な薬物治療を目の前にして、診断偏重だった当時の医療のなかで新たな治療学の幕開けを感ぜずにはいられませんでした。
新薬開発では、適正な用法・用量設定に臨床薬理学が重要な役割を担っています。また、Evidence-Based Medicineの時代、臨床薬理学は薬物治療の質を向上させるため、信頼性の高い臨床試験の実施と評価に密接に関係しています。一方、個々の患者に対応した科学的な薬物治療の開発が有効性のみならず安全性からも求められています。不必要な害や危険から患者を守るため、医療安全のうえでも臨床薬理学が果たすべき役割は大きいと考えています。
日常診療における患者は、年齢、性、体格、生活習慣は異なり、種々の併存疾患を抱え、複数の薬を服用している方など様々です。薬物治療における多様性は、患者の個々の特性や背景に応じた治療アプローチの重要性を示しているともいえます。現在、医療は細分化されて専門性が進んでいます。ただこのような時代でこそ領域を超えた横断的視野が必要であります。
臨床薬理学は「臨床における患者のための薬物治療学」であることを肝に銘じ、理事長として取り組んでいく所存です。どうかご支援ご指導のほどお願い申し上げます。
2025年(令和7年)1月
一般社団法人日本臨床薬理学会
理事長 志賀 剛
(東京慈恵会医科大学臨床薬理学講座 教授)